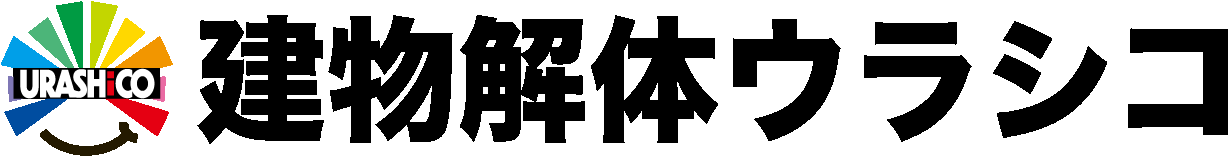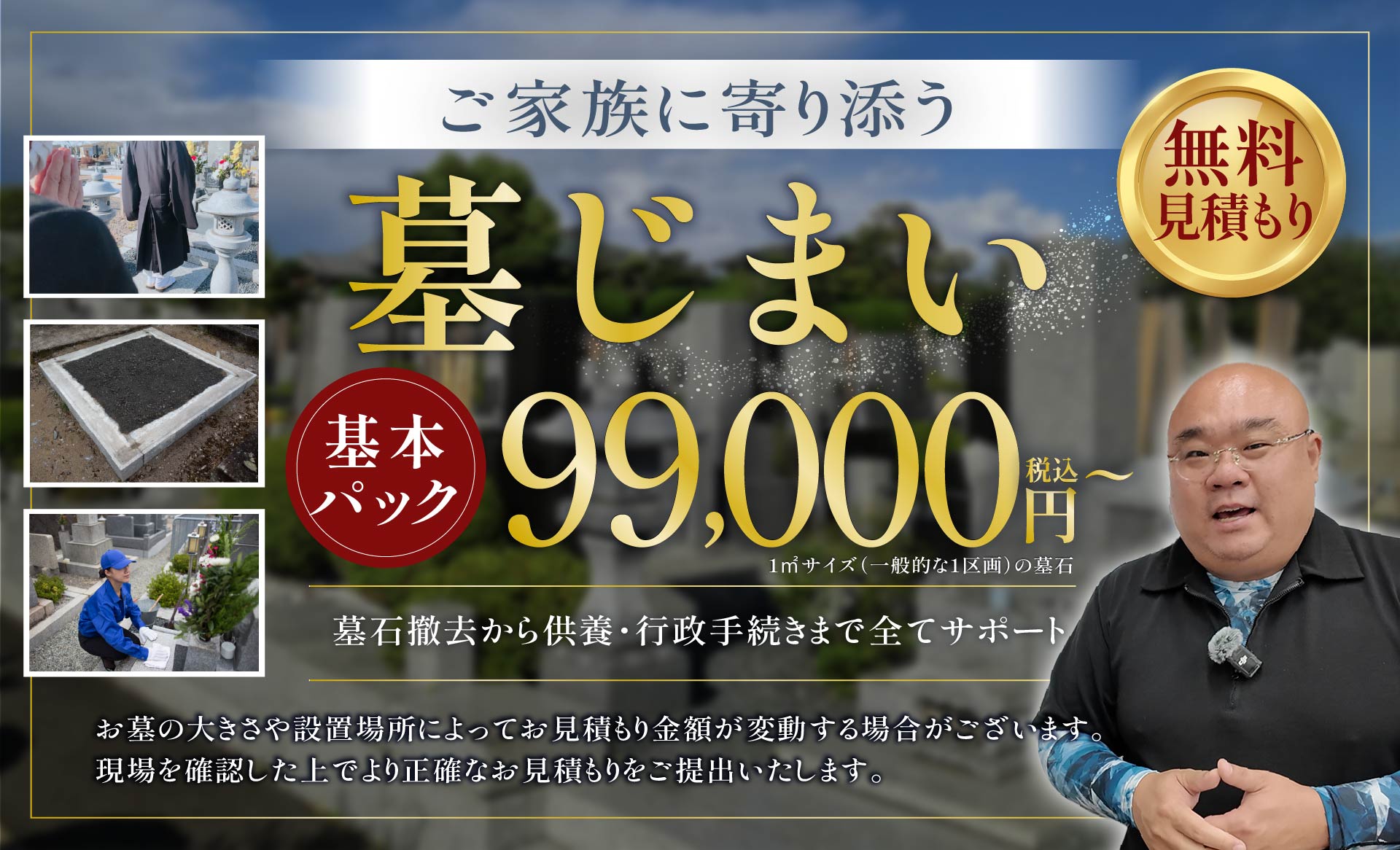木造住宅の解体工事は数百万円単位の大きな出費となるため、「いったいいくらかかるのだろう」「見積もりの妥当性がわからない」といった悩みを抱える方は少なくありません。
今回は木造住宅の解体費用について「坪数・階数ごとの費用目安」と「見積もりのチェックポイント」を整理して解説します。
木造住宅の解体費用の相場

坪単価の目安
木造住宅の解体費用は、一般的に坪単価3万円〜5万円が相場とされています。ただし、この金額は建物の構造や立地条件、解体方法によって大きく変動します。
都市部では人件費や廃棄物処理費が高くなる傾向があり、坪単価4万円〜5万円程度が相場です。一方、地方では3万円〜4万円程度で済むケースが多く見られます。
坪数別費用シミュレーション
具体的な費用イメージを持っていただくために、代表的な坪数での費用例を紹介します。
30坪の木造住宅の場合:解体費用:90万円~150万円
- 平屋:90万円~120万円程度
- 2階建て:120万円~150万円程度
50坪の木造住宅の場合:解体費用:150万円~250万円
- 平屋:150万円~200万円程度
- 2階建て:200万円~250万円程度
※上記は目安金額であり、立地条件や付帯工事の内容により変動します。
平屋と2階建てで費用が変わる理由
同じ坪数でも平屋と2階建てでは解体費用に差が生じます。その理由は以下の通りです。
基礎部分の違い 平屋は建築面積が大きくなるため、基礎の解体範囲も広くなります。基礎の解体は重機による作業が中心となり、面積が広いほど時間と費用がかかります。
作業効率の違い 2階建ての場合、上階から順番に解体していく必要があり、足場の設置や養生にも配慮が必要です。また、高所での作業となるため安全対策も重要で、これらが費用に反映されます。
解体費用の内訳

解体工事の費用は、主に以下の4つの項目で構成されています。それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。
解体工事費
建物本体を解体する作業にかかる費用です。重機による解体作業や手作業による細かい部分の解体、作業員の人件費などが含まれます。
廃棄物処理費
解体によって発生した廃材を適切に処理するための費用です。木材、コンクリート、金属類、石膏ボードなど、材質によって処理方法や費用が異なります。
付帯工事費
建物本体の解体以外に必要となる工事費用です。具体的には以下のような項目が含まれます。
- 足場・養生設置費:近隣への粉塵飛散防止や作業員の安全確保のため
- 家電・家具処分費:エアコンや冷蔵庫など、残置されたものの処分
- 重機回送費:解体重機を現場まで運搬する費用
- 整地費:解体後の土地を平らに整える作業
諸費用
各種手続きにかかる費用や現場管理費などです。建設リサイクル法に基づく届出費用や、工事期間中の現場監督費用などが含まれます。
見積もりの計算方法と具体例

木造住宅の解体費用は、以下の式で概算できます。
坪単価 × 延床面積 + 付帯工事費 = 解体費用
この計算方法を使って、具体的な例を見てみましょう。
30坪2階建ての計算例
- 延床面積:30坪
- 坪単価:4万円(都市部の相場)
- 基本解体費:30坪 × 4万円 = 120万円
- 付帯工事費:30万円(足場、養生、整地など)
- 総額:150万円 ※諸費用除く
50坪平屋の計算例
- 延床面積:50坪
- 坪単価:3.5万円(地方の相場)
- 基本解体費:50坪 × 3.5万円 = 175万円
- 付帯工事費:35万円(基礎面積が広いため割高)
- 総額:210万円 ※諸費用除く
見積書をチェックするポイント
同じ建物の解体でも、業者によって見積額に差が生じるのは以下のような理由があります。
- 構造に対する判断の違い 建物の劣化状況や使用材料の判断により、必要な作業量の見積もりが変わります。
- 立地条件の評価 道路幅や近隣との距離、重機の搬入経路などの評価が業者によって異なります。
- 解体方法の違い 手壊しを多用するか、重機中心で進めるかによって人件費と機械費のバランスが変わります。
見積書比較のチェックリスト
見積書を比較する際は、以下の6項目を重点的にチェックしましょう。
◯ 地中障害物
- 地中に埋設された配管や基礎の一部などの処理費用があるか
- 発見時の追加費用についての取り決めが明記されているか
◯ アスベスト
- 事前調査費用が適切に計上されているか
- アスベスト含有材料が発見された場合の処理費用について説明があるか
◯ 残置物
- 家具や家電など、残されたものの処理方法と費用が明確か
- 事前処分と業者処分のコスト比較がなされているか
◯ 人件費
- 作業員の人数と作業日数が明記されているか
- 技能工と普通作業員の区分が適切か
◯ 産業廃棄物処理
- 廃材の種類別処理費用が詳細に記載されているか
- マニフェスト(管理票)の発行費用が含まれているか
◯ 家屋構造・立地条件
- 建物の構造(在来工法、2×4など)が正しく把握されているか
- 接道条件や近隣環境が適切に評価されているか
良い見積書と悪い見積書の違い
良い見積書の特徴
- 工事項目が細かく分類されている
- 各項目の数量と単価が明記されている
- 追加工事が発生する可能性とその条件が説明されている
- 廃棄物の処理方法が具体的に記載されている
悪い見積書の特徴
- 「解体工事一式」のような大雑把な記載
- 数量や単価の根拠が不明
- 追加費用について説明がない
- 処理業者名や処理施設名が記載されていない
解体費用を抑えるコツ

解体費用を適正価格にするためのポイントをご紹介します。
残置物をあらかじめ処分する
家具や家電製品などの残置物は、可能な限り事前に処分することで、10万円〜30万円程度のコスト削減が期待できます。
建て替えや土地活用の業者にまとめて依頼する
建て替えを予定している場合は、建築業者に解体工事も含めて依頼することで、中間マージンを削減できる可能性があります。土地活用を検討している場合も、不動産会社や建設会社に相談することで、トータルコストを抑えられることがあります。
相見積もりを取る
複数の業者から見積もりを取ることで、適正価格がわかります。2〜4社程度から見積もりを取得し、内容を比較検討することをおすすめします。ただし、極端に安い見積もりには注意が必要です。後から追加費用が発生するリスクがあります。
補助金制度の活用
多くの自治体で、老朽化した住宅の解体に対する補助金制度が設けられています。
- 老朽危険家屋除却費補助金(解体費用の一部を補助)
- 空き家対策補助金(空き家の解体促進のため)
- 住宅・建築物安全ストック形成事業(耐震性不足の建物対象)
補助金の金額は自治体により異なりますが、解体費用の10%程度を補助するケースが多く見られます。ただし、申請には条件があり、事前の届出が必要な場合がほとんどです。
まとめ
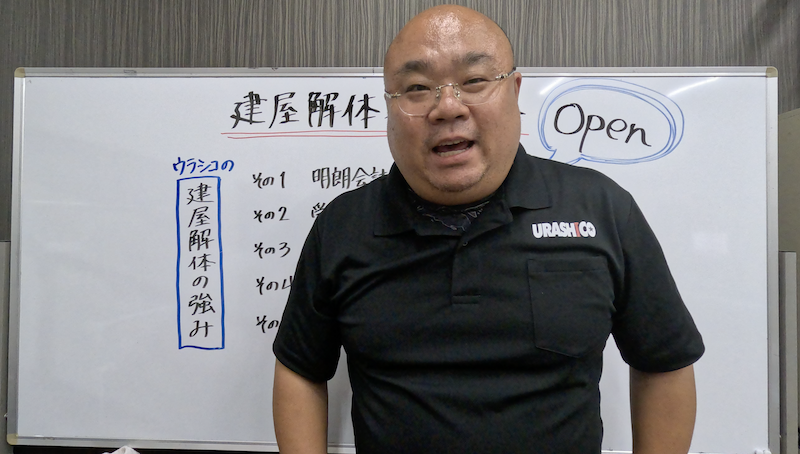
木造住宅の解体費用は、坪数と階数によって大きく変動し、30坪で90万円〜150万円、50坪で150万円〜250万円が一般的な相場となります。費用の内訳は解体工事費、廃棄物処理費、付帯工事費、諸費用の4つに分かれており、それぞれの内容を理解しておきましょう。
見積書を検討する際は、地中障害物、アスベスト、残置物、人件費、産業廃棄物処理、立地条件の6項目をチェックすることで、後々のトラブルを回避できます。
最も重要なのは、信頼できる解体業者に依頼することです。適正価格であることはもちろん、近隣への配慮や安全管理、法令遵守など、総合的に判断して業者を選択することが、安心して解体工事を進めるための近道となります。
ウラシコでは解体工事・原状回復に10年以上の実績を持ち、豊富な経験と確かな技術で対応いたします。まずはお気軽にご相談ください。