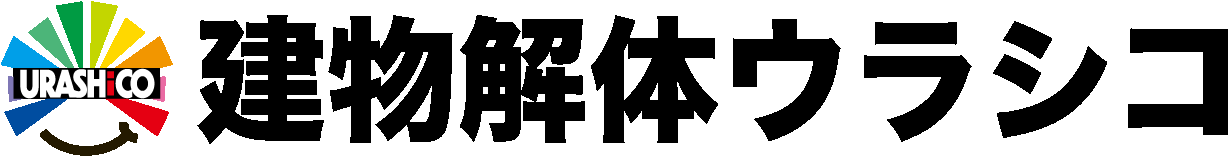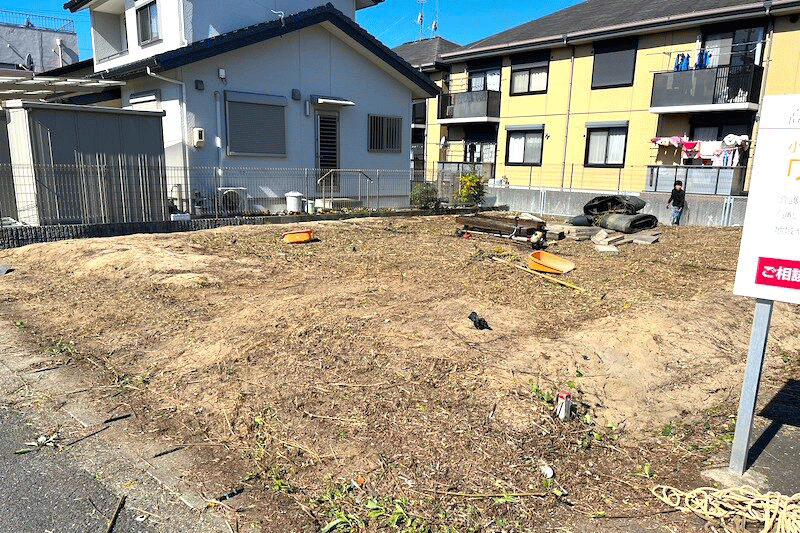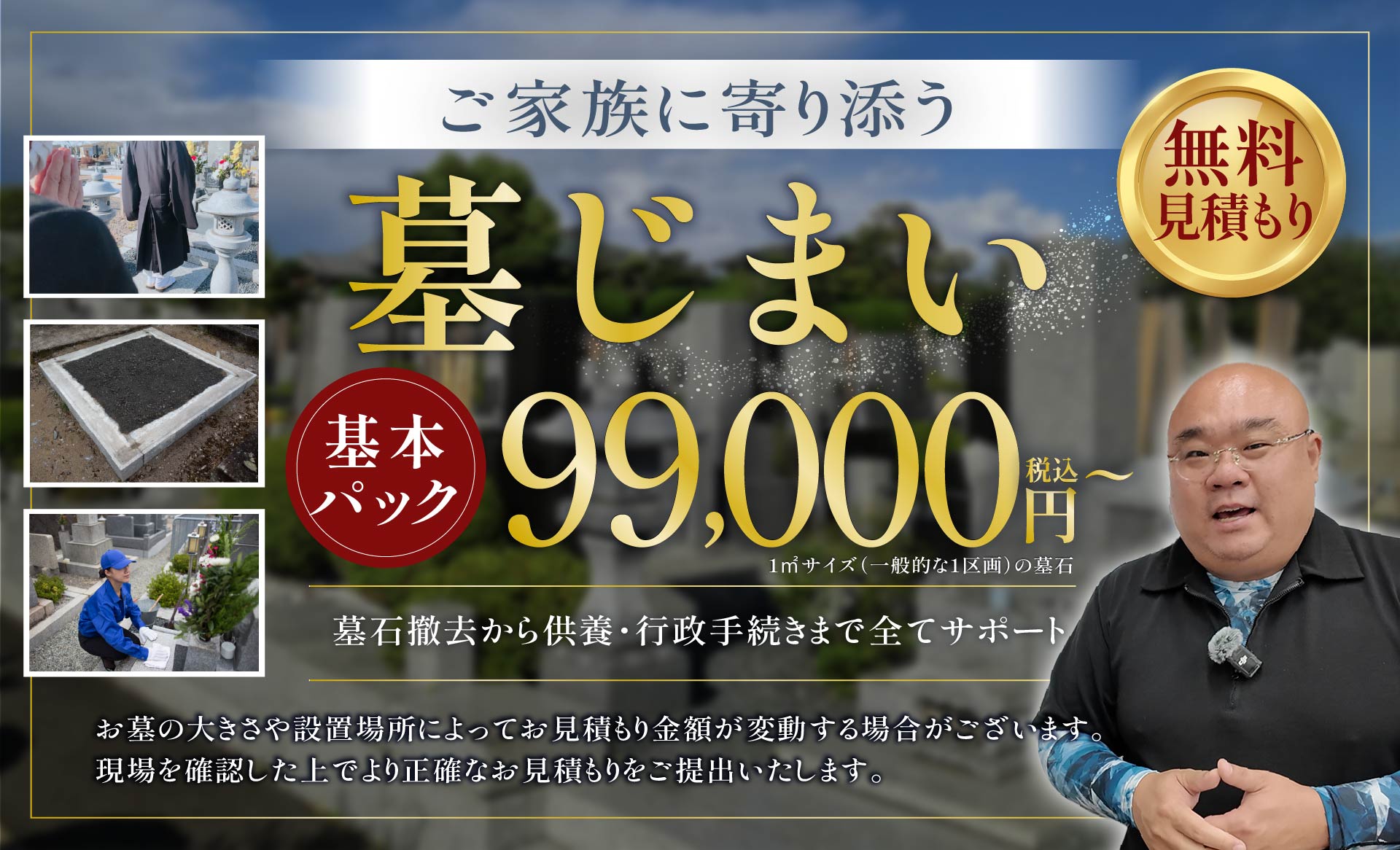少子高齢化や人口減少の影響で、空き家の数が全国的に増加しています。「実家を相続したが住む予定がない」「離れた場所へ住んでいるため管理が難しい」といった理由から空き家となってしまうケースが増え、その後の対応に頭を悩ませる方も少なくありません。
空き家を放置すると、倒壊や火災、景観の悪化などの問題が発生するおそれがあり、最終的に「解体」が必要になる場合もあります。しかし、住んでいない家の解体費用は誰が支払うべきなのでしょうか?
今回は空き家の解体費用について、所有権や相続との関係をわかりやすく解説します。
増え続ける空き家問題と解体の必要性

日本の空き家問題は年々深刻化しています。総務省の調査によると、全国の空き家数はおよそ900万戸(2023年時点)とされ、今後さらに増加すると予測されています。
空き家が放置されると、近隣住民の生活環境に悪影響を及ぼすことがあります。たとえば、建物の老朽化による倒壊のリスクや、雑草やごみの不法投棄による衛生面の悪化、防犯面での不安などが挙げられます。そのため、空き家を解体し、地域の安全や景観を守ることが求められています。
空き家の解体費用は誰が払う?

空き家を解体するには百万円以上の費用が必要になります。では、その費用を負担するのは誰なのでしょうか?ここでは、解体費用を誰が払うのかについて解説します。
所有者(相続人)が負担する
空き家の解体費用は、法律上「建物の所有者」が支払うことが原則とされています。つまり、空き家を所有している人が責任をもって費用を負担しなければなりません。
もし所有者が亡くなっている場合は、相続人がその権利と義務を引き継ぐ形になります。相続の順序は法律で定められており、第一順位として配偶者、次に子・孫・ひ孫などの直系卑属、そして第三順位として両親や祖父母などが対象になります。
相続人が複数いる場合は、共有名義となることがあり、その場合の解体費用も原則として共有者で分担する形になります。
相続放棄すれば支払わなくて良い?
空き家を含む財産を相続したくない場合、「相続放棄」という手続きがあります。これは家庭裁判所に申し立てを行い、正式に相続人でないことを認めてもらう制度です。ただし、単に「相続したくない」と思っているだけでは放棄したことにはなりません。手続きには期限があり、原則として被相続人の死亡を知った日から3か月以内に行う必要があります。
また、相続放棄をした場合でも、誰かが財産を管理しなければならないため、「相続財産清算人」の選任を裁判所に依頼する必要があります。この清算人が、空き家を含む財産の管理・処分・債務整理などを行うことになります。手続きには時間と労力がかかるため、相続放棄を選ぶ際には専門家に相談するのが安心です。
解体費用の相場と費用が高額になるケース
空き家を解体するには、建物の構造や立地、敷地の条件などによって大きく費用が変わるため、事前に相場を把握しておくことが重要です。木造住宅の解体費用は、一般的に1坪あたり3万円〜5万円程度が相場とされています。たとえば30坪の木造住宅であれば、90万円〜150万円程度が目安です。
一方、鉄骨造やRC(鉄筋コンクリート)造の建物になると、構造が頑丈なぶん解体に手間がかかるため、坪単価は5万〜9万円、場合によってはそれ以上となることもあります。また、費用が高額になるケースとして、アスベスト含有の建物があげられます。
アスベストは健康被害を引き起こすおそれがあるため、専門業者による適切な処理が必要です。さらに、地中から廃材や古い基礎、浄化槽などが出てきた場合にも、追加費用が発生する可能性があります。これらのリスクを見越して、解体業者との事前打ち合わせや現地調査をしっかり行い費用を確認しておくことが必要です。
費用負担を軽減する制度や補助金を活用しよう

空き家の解体には多くの費用がかかりますが、負担を軽減するための支援制度が設けられている場合があります。解体を検討している方は、補助金の活用も視野に入れておくとよいでしょう。
空き家解体で利用できる補助制度
名古屋市では、「名古屋市老朽危険空家等除却費補助金」という空き家の解体に対する補助金制度が設けられています。補助の対象となるには、建物が倒壊の危険性があると判断されることや、固定資産税の納付状況に問題がないことなど、条件が細かく定められています。補助金の支給金額はそれぞれ異なりますが、最大80万円の補助金受け取りが可能です。
申請時に注意すべきポイント
補助金の申請は、解体工事に着手する前に申請書を提出する必要があります。事後申請は認められないケースがほとんどのため、まずは自治体の窓口に問い合わせて、制度の有無や申請手順、必要書類を確認しましょう。
また、補助金の予算には限りがあり、年度の途中で受付が終了することもあるため、早めの対応が肝心です。加えて、補助金が交付された場合でも、自己負担が完全にゼロになるわけではないことを理解しておく必要があります。
空き家トラブルを防ぐために今できること

空き家に関するトラブルは、費用面だけでなく、相続人同士の意見の食い違いや管理の責任などさまざまな要素が絡み合います。問題が複雑化する前に、できることを一つずつ進めておくことが重要です。
実家の今後を家族で話し合っておく
空き家になりそうな実家については、親が元気なうちから家族間で話し合っておくことが大切です。「誰が住むのか」「売却するのか」「解体するのか」など、方向性を共有しておくことで、相続後のトラブルを防げます。また、将来的に空き家になった場合に備え、解体や相続にかかる費用についても情報を集めておくと安心です。
専門家(司法書士・行政書士・解体業者)への相談
空き家の所有や相続に関する問題は、法律や税制、建築の知識が必要になることが多く、個人だけで解決するには難しい場合があります。
そのため、司法書士や行政書士といった専門家に早めに相談し、手続きや書類作成のサポートを受けるのが得策です。また、解体業者に相談することで、正確な費用見積もりや補助制度の情報なども得られます。信頼できるパートナーを見つけておくことが、将来の備えにつながります。
相続登記を早めに済ませておく
2024年4月から、相続による不動産取得に対して「相続登記の義務化」が始まりました。これにより、不動産を相続した人は3年以内に登記を行う必要があり、怠った場合は過料が科される可能性があります。
相続登記を行わずに放置してしまうと、誰が所有しているか不明確となり、解体や売却など次の手続きが進まないだけでなく、相続関係のトラブルに発展するリスクもあります。早めに手続きを行っておくことで、空き家の管理や処分をスムーズに進めることができ、のちの負担軽減に繋がるでしょう。
まとめ

空き家となった実家をそのまま放置すると、さまざまな問題を引き起こす可能性があります。解体という選択肢を取る場合、費用は原則として所有者、もしくは相続人が負担することになります。
相続放棄や補助制度の活用など、費用面での工夫はありますが、どのような選択をするにしても「知らないまま放置しないこと」が大切です。今のうちから家族と話し合い、必要に応じて専門家の力を借り、将来のトラブルを未然に防ぎましょう。