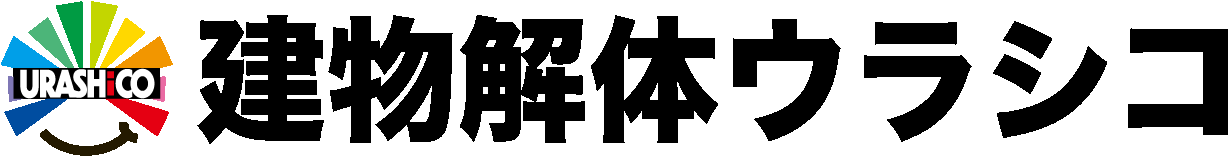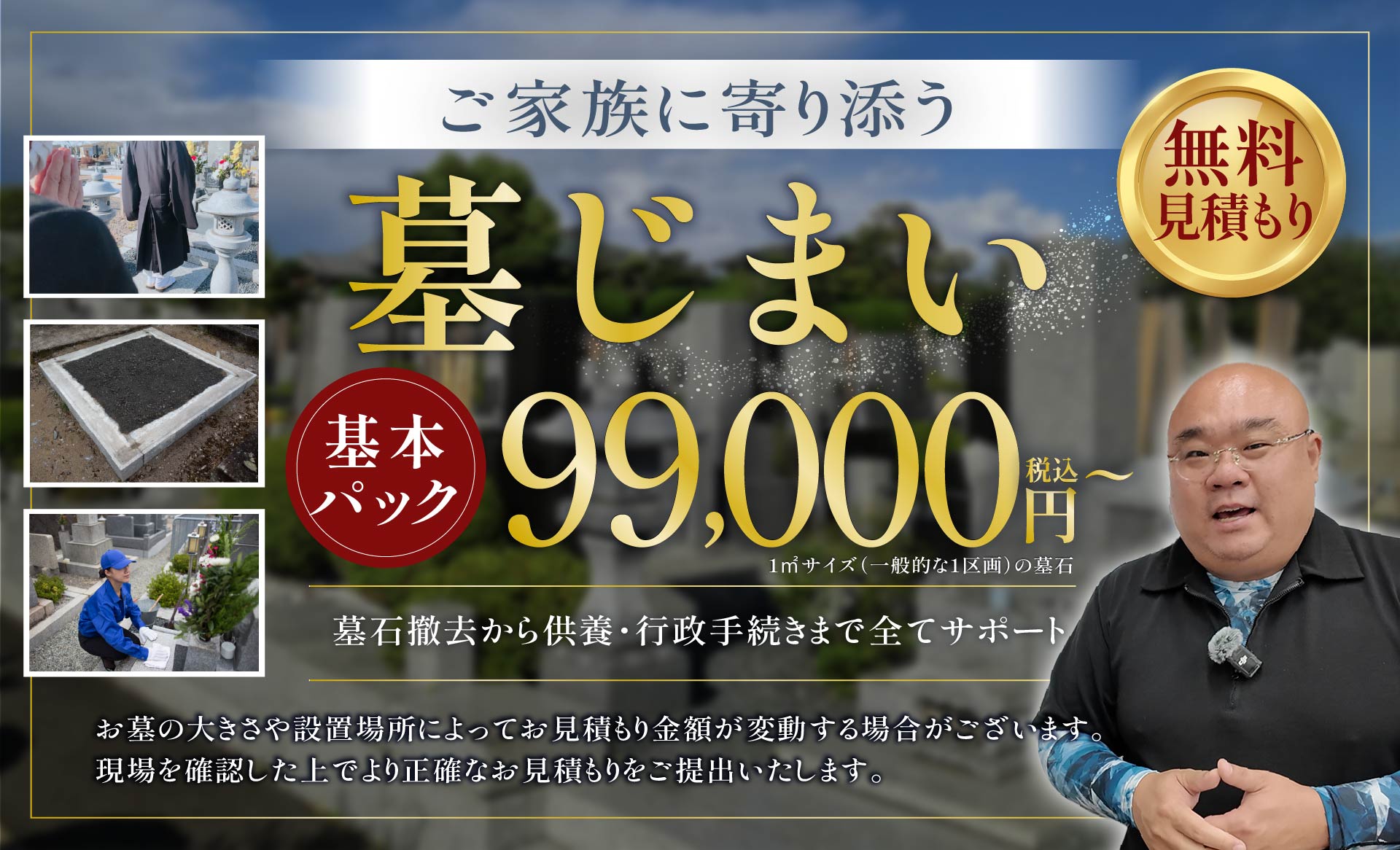相続した家が空き家だったとき、「使う予定もないし、維持費もかかるから相続放棄したい」と検討中の方は多いのではないでしょうか。しかし、空き家を相続放棄したあと、その物件がどうなるのかまでは、あまり知られていないのが現状です。
今回は空き家の解体工事のご相談を長年お受けしてきた経験から、空き家の相続放棄後の流れや注意点(残念ながら悲惨な結果になってしまった点)を、わかりやすく解説します。現場目線のリアルな情報となっていますのでぜひ最後までご覧ください。
相続が決定したあとの更地化のメリット・デメリットに関してはこちらの動画で解説しています。ぜひこちらも合わせてご参照ください。
相続放棄とは?

相続放棄とは、一言で言えば亡くなった方(親や配偶者)の財産を一切引き継がない手続きです。相続の対象には、預金といった資産だけでなく、空き家も相続財産に含まれるため、放棄すれば所有権を持たなくて済みます。
ただし、相続放棄には家庭裁判所での正式な手続きが必要であり、単に物件を放置するだけでは放棄したことにはなりません。手続きを怠ると、思わぬトラブルに巻き込まれるおそれがあるため、法的な対応が求められます。
空き家を相続放棄したらどうなる?

相続放棄手続きが無事に完了し、空き家を相続放棄しても、すぐに完全に無関係になるわけではありません。放棄したあとの空き家はどうなるのか、誰の手に渡るのかなど、事前に知っておくべきポイントがあります。
注意すべきは、他の相続人との関係や、管理責任の所在です。場合によっては、相続放棄が原因で家族間に不和が生じることもあるため、状況を整理してから行動しなければなりません。まずは、所有者、管理責任の観点を整理しましょう。
放棄後、空き家の所有者は誰になる?
相続放棄をすると、その人が相続人ではないものとみなされます。そのため、次順位の相続人に相続権が移ります。たとえば被相続者の子どもや孫が放棄すれば、次は直系尊属が相続の対象となる可能性があります。
しかし、誰も相続を希望しない場合、空き家は「相続人不存在」となり、最終的には家庭裁判所の手続きを経て国や自治体が対応する形になります。権利がすぐに移転するわけではありませんが、一定期間、管理者不在のまま放置されることもあります。
ここで重要なポイントが、”相続放棄は個人単位で行うもの”であるということです。自分が放棄しても、他の相続人が手続きしない限り、その人たちに相続権と管理責任があります。その結果、空き家の固定資産税や修繕費などを他の相続人が負担することになり、予期せぬトラブルの原因になる場合もあります。
相続放棄を検討する際には、自分の判断だけで進めるのではなく、他の相続人とも事前にしっかりと話し合いをすることが重要です。
管理責任は本当にゼロになる?
相続放棄をしても、管理責任が即座にゼロになるわけではありません。家庭裁判所での手続きが完了するまでは、空き家に対する最低限の管理が求められる場合があります。
また、相続人が誰もいない状態が長引くと、空き家が倒壊したり火災が起きたりした際、元相続人として一時的に責任を問われることもあります。完全に関係を断つには、法的な手続きの完了と、空き家の状態に応じた対応が必要です。
相続放棄から解体までの一般的なパターン

空き家の相続放棄を決めた場合でも、すぐに解体や処分が進むわけではありません。実際には、相続放棄の手続きを経て、最終的に誰が管理や解体を行うかが明確になるまで、いくつかの段階を踏む必要があります。ここでは、相続放棄から解体までの一般的な流れを紹介します。
1. 相続放棄に必要な書類を用意する
相続放棄を行うには、いくつかの必要書類を揃えなければなりません。主に必要とされるのは、以下の書類です。
・相続放棄申述書
・被相続人の住民票除票
・申述する人の戸籍謄本
ただし、被相続人との関係によって上記のほかにも必要な書類があるため、事前に専門家へ確認しておくのがおすすめです。これらの書類は役所や法務局などで取得できるため、早めに準備しておくと手続きがスムーズに進みます。不備があると手続きがやり直しになる可能性もあるため、間違いがないよう書類の作成、準備を進めましょう。
2. 家庭裁判所へ相続放棄を申し立てる
書類を準備したら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述を行います。原則として被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以内に手続きが必要です。申述書や添付書類を提出し、裁判所の受理を待ちましょう。提出後すぐに結果が出るわけではなく、照会書のやりとりなどのプロセスを経て、正式に認められるかどうかが決まります。
3. 家庭裁判所からの照会書に回答する
相続放棄の申述を提出すると、裁判所から照会書が送付されます。照会書とは、相続放棄が本人の意思によるものかを確認するための書類です。記入内容に虚偽や不備があると、申述が却下される可能性もあるため、誠実かつ正確に記入しましょう。
4. 相続放棄申述受理証明書が届く
裁判所による審査を経て相続放棄が正式に認められると、「相続放棄申述受理証明書」が発行されます。これにより、相続人としての立場がなくなり、空き家に関する所有権も消失します。この証明書は、金融機関や他の行政手続きで提示を求められることもあるため、大切に保管しておく必要があります。
5. 誰が空き家を管理・解体するのか決まる
相続放棄が完了した後、その空き家の管理や解体は次順位の相続人に引き継がれることになります。しかし、すべての相続人が放棄する場合、家庭裁判所の手続きにより「相続財産管理人」が選任され、空き家の処分を担当します。
相続財産管理人とは
相続財産管理人は、誰も相続を引き受けない財産(特に空き家など)を安全に処理するための法的仕組みです。特に、老朽化空き家や借金付きの物件では「全員相続放棄 → 管理人選任 → 解体・処分」といった流れが必要になります。
具体的には、家庭裁判所により第三者(通常は弁護士など)が選ばれます。ここで注意が必要なことが相続財産管理人への依頼には、予納金と呼ばれる費用が必要になります。これは、申立人が負担が負担しなければなりません。
費用は10~100万円程度になります。費用の振れ幅が大きいのは、放棄する空き家の価値によって変動するからです。つまり、相続人が全員相続放棄したとしても、相続財産管理人への予納金は必ず支払う必要があります。
6. 解体工事
解体が決まった場合は以下のような形で解体が実施されます。各解体作業の完了後は、建物の滅失登記を行政に提出して完了となります。
・次順位の相続人が相続した場合:次順位の相続人が解体費用を負担し解体工事を実施します。
・相続財産管理人に依頼した場合:相続財産管理人が解体費用を負担し解体工事を実施します。
ほとんどが上記の2パターンになりますが、「全員相続放棄 → 管理人選任もできない」というパターンも稀にあります。相続人の全員が相続権を放棄し予納金を支払わないというパターンです。そのような場合は、税金を使って行政代執行という形で実施されます。
相続放棄の手続き期間と注意点

相続放棄には期限があり、その期間を過ぎると放棄が認められないこともあります。また、相続放棄したから完全に無関係になると思い込んでしまうと、後々のトラブルに巻き込まれるリスクもあるでしょう。ここでは、手続きの期間と放棄時に注意すべき点を紹介します。
相続放棄は3ヶ月以内に手続きが必要
相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に手続きを行う必要があります。この間に何の対応も取らなければ、自動的に「相続を承認した」とみなされます。空き家のような不動産は維持費がかかるため、早めに判断を下すことが重要です。期限を過ぎると、放棄したくても認められないことがあるので注意しましょう。
相続放棄と財産放棄の違いを正しく理解する
相続放棄と似た言葉に財産放棄というものがありますが、これらは意味が異なります。相続放棄は法的に相続人でなくなることを指しますが、財産放棄は相続人のまま、特定の財産を受け取らないという意思表示にすぎません。
そのため、財産放棄をしても責任や義務が完全になくなるわけではないのです。誤って財産放棄を選んでしまうと、空き家の管理責任などが残る可能性もあるため、意味の違いをしっかり理解しておくことが大切です。
放棄しても責任を問われるケース
相続放棄が受理されたとしても、状況によっては責任を問われることがあります。たとえば、空き家の管理を怠った結果、近隣に被害を与えた場合、法的に一時的な管理責任が問われる可能性があります。
また、相続放棄をした人が相続財産を勝手に処分したり利用したりした場合、「単純承認」とみなされて放棄が無効になることもあるため注意が必要です。相続放棄の手続きが完了するまでは、慎重な対応を心がけましょう。
まとめ
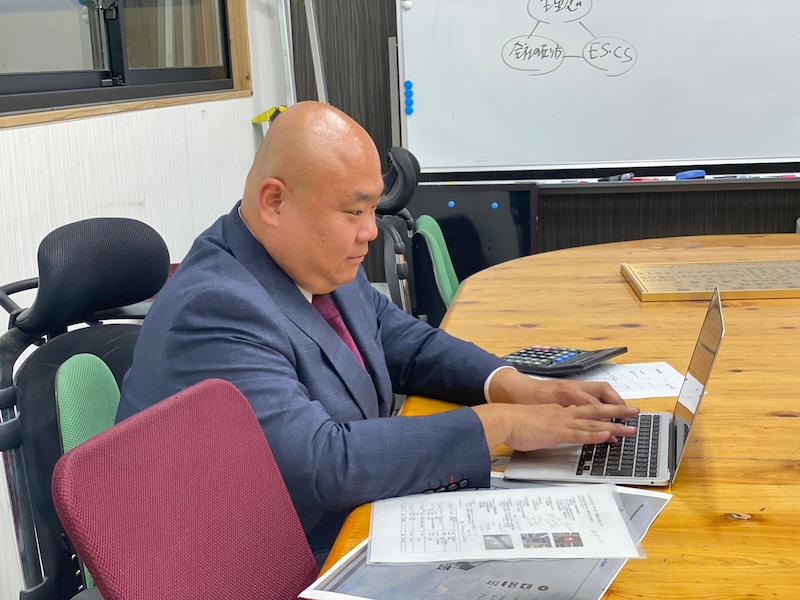
空き家の相続は、維持や管理の手間・費用などが重くのしかかることもあり、相続放棄という選択肢を取る人も少なくありません。しかし、相続放棄をすればすぐにすべての問題から解放されるわけではなく、一定の手続きや責任が伴うことを理解しておく必要があります。
放棄を検討している場合は、3ヶ月という期限を意識しつつ、書類の準備や家庭裁判所への申述を早めに進めることが大切です。また、他の相続人や親族との連携、必要に応じて弁護士など専門家への相談も有効です。
空き家を放棄することは、身軽になる一方で周囲に影響を与える行為でもあります。自分だけで判断せず、冷静に対応していきましょう。もちろん私たちウラシコにもお気軽にご相談いただけますと幸いです。