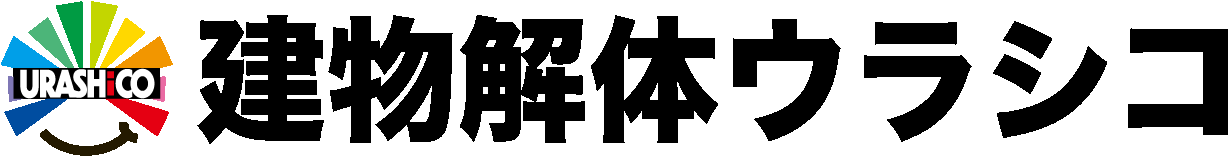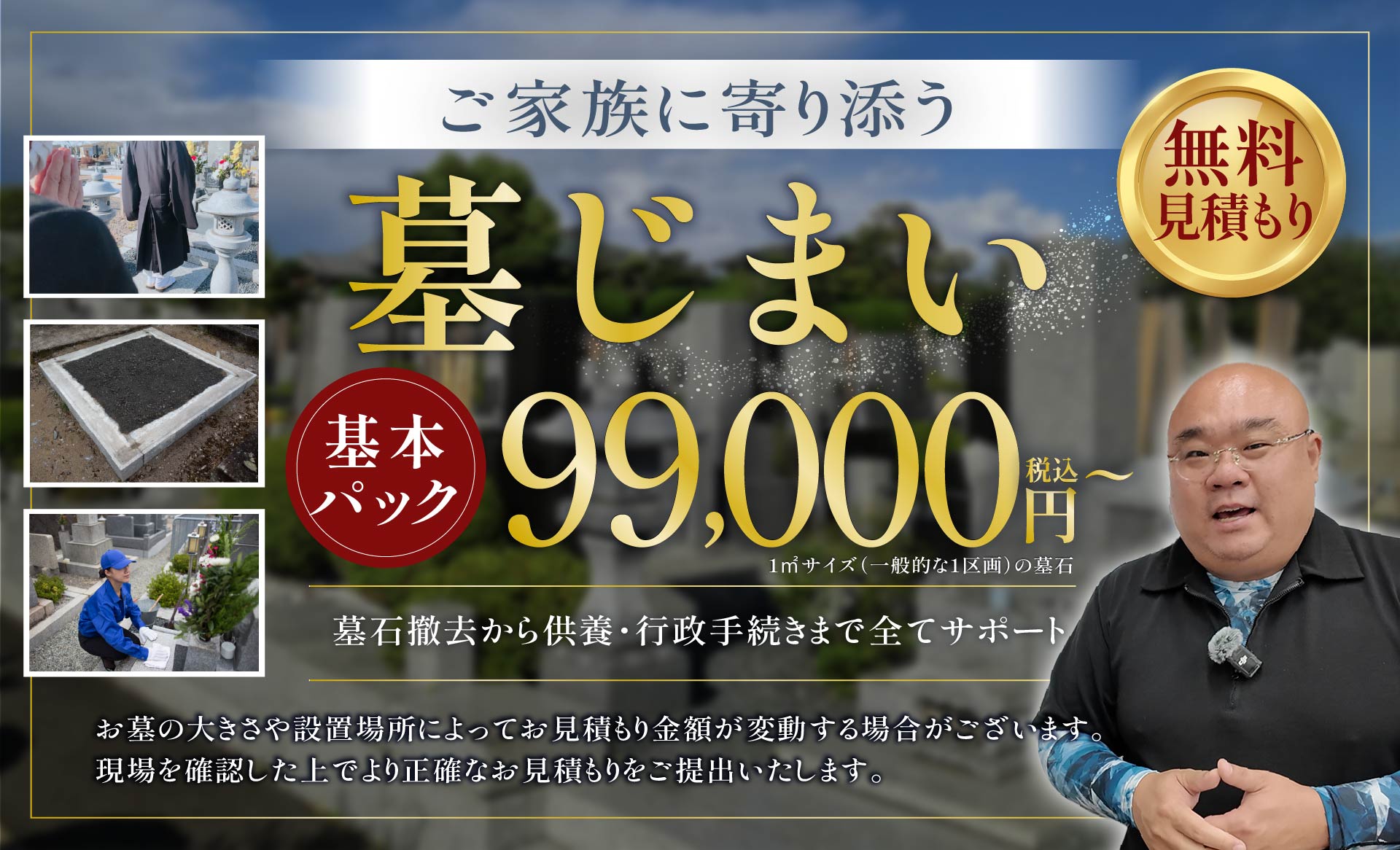日本全国で空き家が増えていることは、ニュースなどで耳にしたことがあるのではないでしょうか。総務省の統計によると、全国の空き家数は増加の一途をたどり、特に老朽化が進んで管理が行き届かない住宅が問題になっています。
空き家を放置すると景観が悪くなるだけでなく、倒壊や火災の危険、害虫や不法侵入といったリスクが生まれ、地域全体の安全や環境にも影響を与えてしまいます。こうした空き家の中で、特に危険と判断されたものが「特定空き家」です。
もし所有する空き家が特定空き家に指定されてしまうと、固定資産税の軽減措置が外れて税金が増えたり、自治体から勧告や命令が下されることになります。
最悪の場合には強制的に解体され、解体費用まで請求されることもあるのです。今回は特定空き家とは何か、誰が判断するのか、指定される基準、そして指定されるとどうなるのかを解説します。
特定空き家とは?基本の定義をわかりやすく解説

空き家とは、単に「人が住んでいない家」のことではありません。法律では「建物が長期間にわたって使用されていない状態」を空き家と定義しています。そしてその中で、周囲に深刻な影響を及ぼすと判断されたものを「特定空き家」と呼びます。
この判断を行うのは市区町村です。自治体が現地を調査し、危険や衛生面の問題があると認めた場合に、市町村長の権限で特定空き家に指定されます。つまり、所有者自身の感覚で「まだ大丈夫」と思っていても、第三者である自治体が「危険」と判断すれば指定されることになります。
特定空き家の判断基準とは?4つのケース

特定空き家に指定されるかどうかは、法律で定められた4つの基準によって判断されます。
- そのまま放置すれば倒壊の危険がある場合
- そのまま放置すれば衛生上有害となる場合
- 管理が行われず、景観を著しく損なっている場合
- 周辺の生活環境を守るために放置が不適切とされる場合
例えば、屋根や外壁が崩れ落ちそうなほど老朽化している、庭にゴミが放置され悪臭や害虫が発生している、外観が荒れ果てて街の景観を壊しているといった状態です。さらに、不法侵入者が出入りして火災や犯罪につながる危険がある場合も対象となります。
以下の表に、判断基準と具体例を整理しました。
| 判断基準 | 具体例 |
| 倒壊の危険 | 地震や台風で崩れる恐れのある建物、外壁のひび割れや屋根の破損 |
| 衛生上の問題 | ゴミの放置による悪臭、害虫・ネズミの発生、雑草やカビの繁殖 |
| 景観の悪化 | 外壁が剥がれている、雑草で覆われ荒れ放題の庭 |
| 生活環境への悪影響 | 不法侵入や放火の可能性、近隣住民の生活への支障 |
このように、判断のポイントは「周囲に迷惑や危険を及ぼすかどうか」です。ただ人が住んでいないというだけでは特定空き家にはなりませんが、放置されて環境に影響を与え始めると、指定される可能性が高まります。
特定空き家に指定されるとどうなる?

特定空き家に指定されると、所有者にはさまざまな不利益が生じます。その中でも大きなものが固定資産税の増加です。住宅が建っている土地には「住宅用地特例」という制度があり、固定資産税が最大6分の1に軽減されています。しかし、特定空き家に指定されるとこの特例が適用されなくなり、税金が大幅に増える可能性があります。
また、自治体は所有者に対して段階的に指導を行います。最初は助言や指導から始まり、改善されなければ勧告、さらに命令が下されます。命令に従わなければ、50万円以下の過料に処せられる場合があります。
それでも放置した場合、最終的には「行政代執行」が行われ、自治体が強制的に建物を解体し、その費用を所有者に請求します。解体費用は数百万円にのぼることもあり、突然大きな負担を背負うことになってしまうのです。
このように、特定空き家に指定されることは税金や費用の面だけでなく、精神的な負担も非常に大きいといえるでしょう。
特定空き家にしないための主な対処法

特定空き家に指定される前に、所有者ができる対策はいくつかあります。代表的な方法を挙げると以下のとおりです。
- 空き家バンクに登録して売却や賃貸に活用する
- リフォームしてシェアハウスや民泊として利用する
- 空き家の管理サービスを利用して定期的に点検や清掃を行う
- 不動産会社の活用サービスを利用し、運営を任せる
- 老朽化が進んでいる場合には思い切って解体する
いずれの方法にもメリットとデメリットがありますが、重要なのは「放置しないこと」です。何もせずに時間が経つと、建物はさらに劣化し、対処が難しくなります。早めに動くことで、将来の大きな負担を避けることができるのです。
解体という選択が有効なケースとは?

特定空き家の指定を避けるための方法はいくつもありますが、解体という選択肢は根本的な解決策になります。建物の老朽化が進み、倒壊の危険がある場合や、修繕費用や管理コストがかさみ続けて維持が難しい場合には、解体がもっとも合理的です。
また、更地にすれば土地の活用方法が広がります。売却することもできますし、新たに建物を建てることも可能です。自治体によっては解体費用の一部を補助する制度が設けられていることもあり、経済的な負担を軽減できる場合もあります。
確かに更地にすると固定資産税が上がることがありますが、土地を売却したり、新しい住宅を建てたりすればその負担は解消されます。何よりも「倒壊の危険がなくなる」「近隣からの苦情がなくなる」という安心感は大きな価値があります。
空き家を解体するか残すかの判断基準については以下のYouTube動画で詳しく解説しています。ぜひこちらも合せてご参照ください。
解体工事を検討するなら、まずは専門業者に相談を

空き家の所有者にとって「解体」という選択は大きな決断ですが、不安を抱えたまま放置するよりもはるかに前向きな方法です。専門の解体業者に相談すれば、現地を調査して建物の状態を確認し、見積もりを出してもらえます。その結果をもとに、リフォームや売却といった他の選択肢と比較することもできます。
解体業者に相談することは、「どのくらいの費用がかかるのか」「工期はどのくらいなのか」といった具体的な情報を得るきっかけになります。放置して自治体から命令や罰則を受ける前に、まずは相談してみることが、最も安心で賢明な選択といえるでしょう。
ウラシコではお客様目線でわかりやすい見積書を作成しております。細目を細かく設定し、明朗会計、適正価格でお見積もりいたします。LINEでも対応しております!
まとめ
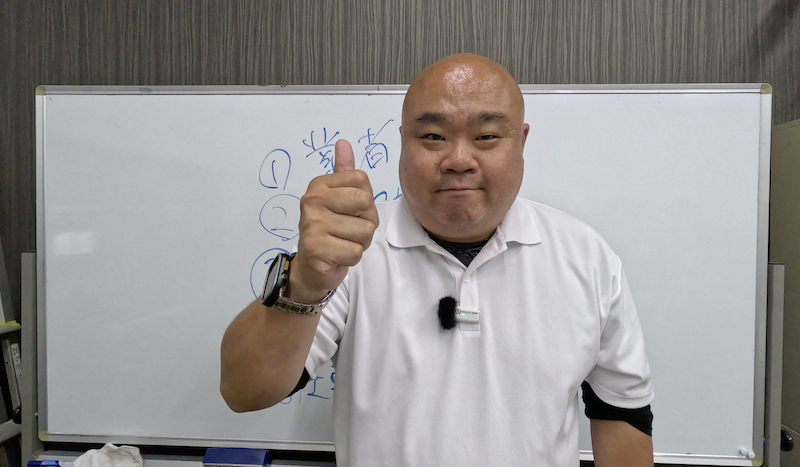
特定空き家とは、単に人が住んでいない家ではなく、倒壊の危険や衛生面の問題、景観の悪化などによって周囲に迷惑をかける可能性がある建物を指します。その判断基準は市区町村が管理します。
特定空き家に指定されると固定資産税の軽減措置が外れて税金が増加し、命令に従わなければ過料が科され、最終的には行政代執行によって解体されるリスクもあります。
空き家を放置することは、近隣とのトラブルや災害時の危険、不法侵入の恐れなど、さまざまなリスクを抱えることにつながります。早めに空き家バンクの利用やリフォーム、管理サービスといった方法を検討し、老朽化が進んでいる場合には解体も前向きに考えることが重要です。
特に解体は、根本的にリスクを取り除き、土地を有効に活用できる手段です。確かに費用はかかりますが、倒壊や苦情といった不安から解放され、安心して将来を描けるというメリットがあります。
「このまま放置して大丈夫だろうか」と不安を感じたら、まずは専門の解体業者に相談してみてください。現地調査や見積もりを通じて具体的な状況を把握することで、最適な解決策が見つかり、所有者にとっても地域にとっても安心につながるはずです。