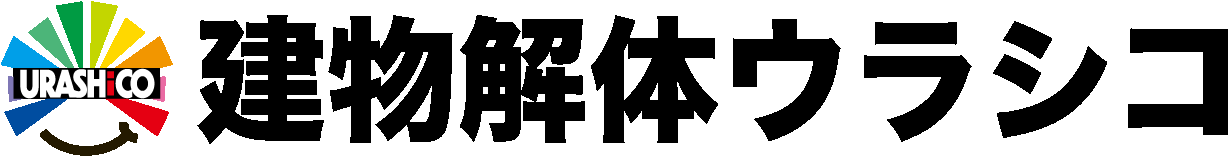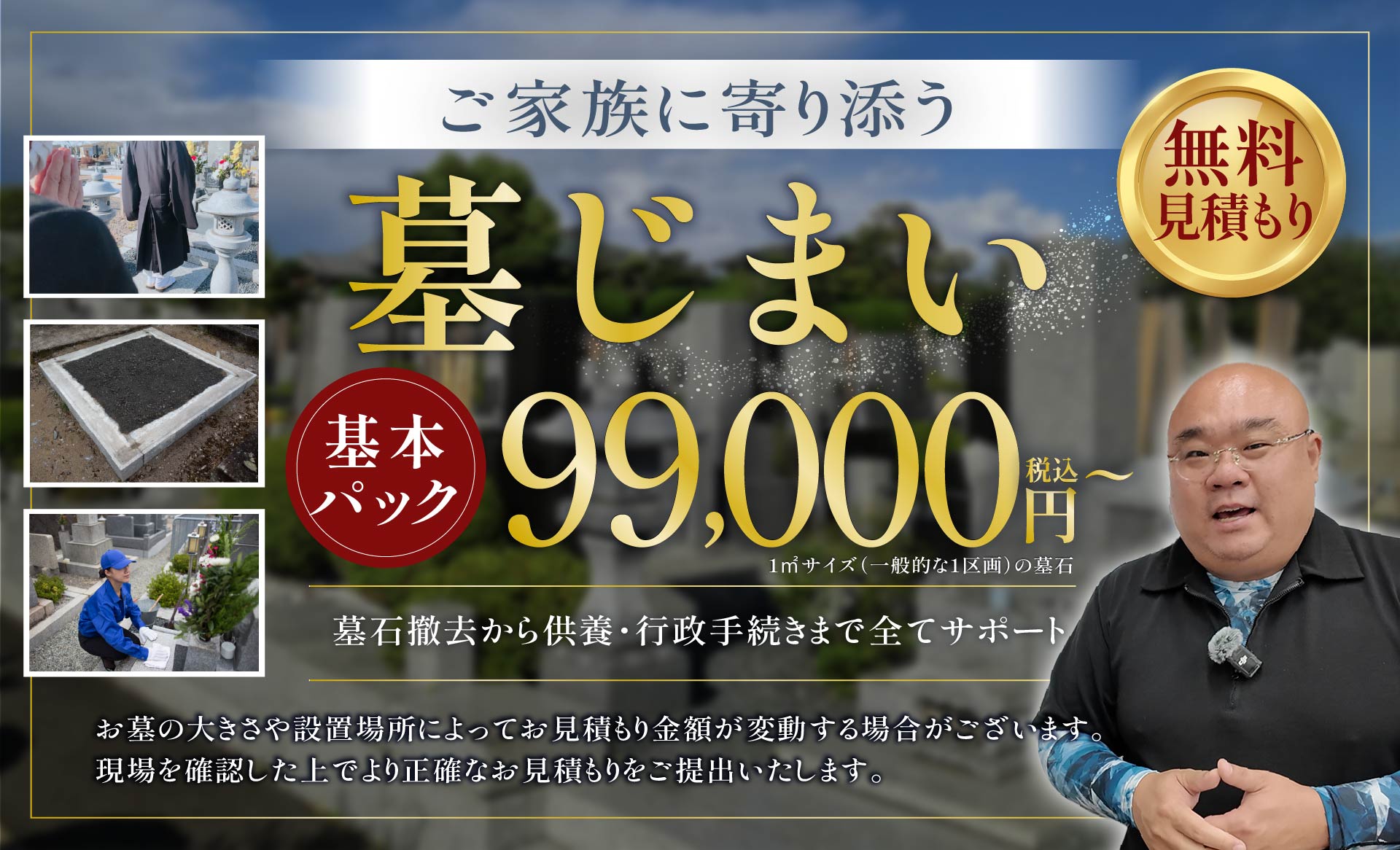家の解体費用は数百万円になることも多く、家計にとって大きな負担です。だからこそ「確定申告で節税できるのでは?」と考える方も多いのではないでしょうか。
解体費用が控除できるかどうかは、解体の目的や建物の用途によって大きく変わります。正しい知識がないまま申告してしまうと、税務署から指摘を受けたり、節税のチャンスを逃してしまったりする可能性もあります。
今回は「解体費用は控除できるのか」「どんな計上をすればいいのか」「申告のときに気をつけることは何か」を整理しました。正しい知識を身につけて、安心して確定申告に臨みましょう。
家の解体費用は確定申告で控除できる?

結論から言うと、家の解体費用は目的や建物の用途によって、経費・控除できる場合とできない場合があります。
判断のポイントは「事業用なのか」「売却のためか」「生活用なのか」の3つです。税法では、個人の生活に関する支出(家事費)は経費として認められません。一方で、事業や不動産の売却に関する支出は必要経費や譲渡費用として扱われます。
たとえば、賃貸物件として使っていた建物を解体する場合は、事業用資産の処分として経費計上が可能です。逆に、自宅を建て替えるための解体は生活のための支出とみなされるので、控除の対象にはなりません。
同じ解体工事でも目的によって扱いが大きく変わるため、事前に正しい分類を理解しておくことが大切です。
経費計上・控除できるケース
解体費用が経費や控除の対象になる主なケースは次の3つです。
売却のための解体

土地や建物を売却する前に、買い手を見つけやすくするために建物を解体した場合、その費用は「譲渡費用」として控除できます。譲渡費用は売却価格から差し引けるので、譲渡所得税を抑える効果があります。
ただし、解体と売却の間に長い期間が空いてしまった場合や、売却以外の目的が優先されていた場合は譲渡費用として認められないこともあります。契約書や売却の資料をしっかり残し、売却目的であることを明確にしておきましょう。
賃貸物件や店舗など事業用の建物
事業で使っていた建物を解体する場合、その費用は必要経費として計上できます。対象となるのは賃貸アパートや店舗、工場などで、「固定資産除却損」などの勘定科目で処理します。
青色申告をしている場合は、この除却損を他の所得と損益通算できることもあります。さらに、建て替えを前提とした解体なら「建設仮勘定」で処理し、完成後の建物価額に含めて減価償却する方法もあります。
災害など外的要因で取り壊す場合
地震や台風、火災などで建物が壊れ、やむを得ず解体した場合は「災害損失」として控除を受けられます。雑損控除の対象となり、総所得の10%を超える部分や、災害関連の支出から5万円を引いた額を所得から控除できます。
この場合は、市町村が発行する「罹災証明書」などの公的証明が必要です。さらに、保険金で補填される分は控除できないため、受け取った保険金額を把握しておくことが大切です。
目的別の扱い早見表
| 解体の目的 | 扱い | 経費算入の可否 |
| 土地売却のため | 譲渡費用 | ○ |
| 事業用の建物を解体 | 固定資産除却損など | ○ |
| 災害で損壊した住宅 | 災害損失 | ○ |
| 自宅を建替え(生活用→生活用) | 家事費 | × |
| 自宅を建替え(生活用→事業用) | 家事費 | × |
譲渡所得の計算例(売却のために解体した場合)
- 売却価格:3,000万円
- 取得費:2,000万円
- 解体費用:200万円
計算式:
譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)
= 3,000万円 -(2,000万円 + 200万円)
= 800万円
この800万円が課税対象の所得(特例控除を使う前の金額)となります。
控除できないケース
次に控除ができないケースを見ておきましょう。
自宅の建替え
もっとも多い誤解が「自宅を建て替えるための解体費用を経費にできる」というもの。自宅は生活のための建物なので、その解体は税法上「家事費」として扱われ、経費にはなりません。
個人的な理由での事業用建物解体
事業用の建物でも、事業と関係のない個人的な理由で解体し、その跡地に自宅を建てる場合は経費にはなりません。事業継続ではなく、生活のための支出と判断されるからです。
取得した土地の古家解体
古家付きの土地を購入して解体する場合、費用は土地の取得費に含まれます。経費として単独で計上はできず、土地の簿価に加える形になります。将来その土地を売却するときには、この取得費を含めて譲渡損益を計算します。
仕訳・勘定科目の基本

解体費用の仕訳は目的によって変わります。
取り壊しのみの場合
跡地を他の用途に使う場合は「固定資産除却損」として処理します。帳簿価額が残っている場合は、その残額と解体費用を合算して除却損とします。
新築のための解体
建て替えが目的なら「前払金」や「建設仮勘定」で処理します。解体費用を新築の取得費に含め、建物完成後に減価償却します。
災害による損壊
災害で建物を壊すことになった場合は「災害損失」として処理します。この場合も建物の帳簿価額と解体費用を合算して損失額を計算します。
確定申告の手続きと必要書類

解体費用を確定申告で処理するには、必要書類をきちんと揃えておくことが大切です。
必須なのは解体工事の契約書と領収書の原本です。金額や工事内容、工期が明確に書かれているものを保管しておきましょう。また、解体した建物の登記事項証明書(閉鎖謄本)も必要です。
売却目的の解体なら「譲渡所得の内訳書」も必要になります。売却価格から譲渡費用(解体費用を含む)を差し引いて計算するため、正確な金額を記載することが求められます。
確定申告の期間は毎年2月中旬から3月中旬までです。書類に不備があると控除が受けられない場合があるため、余裕をもって準備しましょう。
節税に活用できる特例
解体費用とあわせて、特例を利用することでさらに節税効果が期待できます。
居住用財産の3,000万円特別控除
マイホームを売却する場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度。解体費用を譲渡費用に含め、さらにこの特例を利用することで税負担を大きく減らせます。
相続空き家の3,000万円特別控除(空き家特例)
相続で取得した古い家を解体し、更地として売却する場合も、条件を満たせば最大3,000万円の控除を受けられます。
その他の特例
事業用資産の解体では、減価償却の特例や少額資産の特例が使える場合もあります。青色申告者であれば30万円未満の資産を一括で経費計上できる制度もあるので、小規模工事では有効です。
確定申告での注意点と専門家相談

解体費用の扱いはケースによって判断が難しいこともあります。特に、自宅の一部を事業用にしていた場合や、事業用から居住用に切り替えた場合などは複雑です。
高額な費用がかかるため、迷ったときは税理士に相談するのが安心です。
税務署でも基本的な相談は可能なので、申告前に確認しておくとトラブルを防げます。また各自治体でも「税理士による無料相談」が受けられる場合があります。
まとめ

家の解体費用は「目的」によって確定申告での扱いが変わります。
- 売却のため、事業用建物、災害による解体は控除可能
- 自宅の建て替えなど生活のための解体は控除不可
解体の前に目的を明確にし、書類を整え、正しい勘定科目で処理することが大切です。さらに特例を組み合わせれば大きな節税につながります。複雑なケースでは専門家に相談し、正しい申告を行うことで安心して確定申告ができます。
株式会社ウラシコでは原状回復・内装解体に関するご相談、お見積りは無料で対応しております。ご不明点等ございましたら、私たちにお気軽にご相談ください。