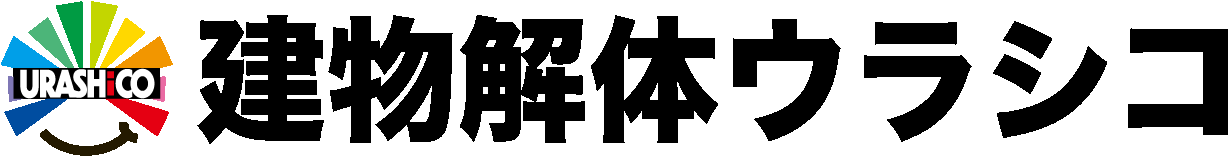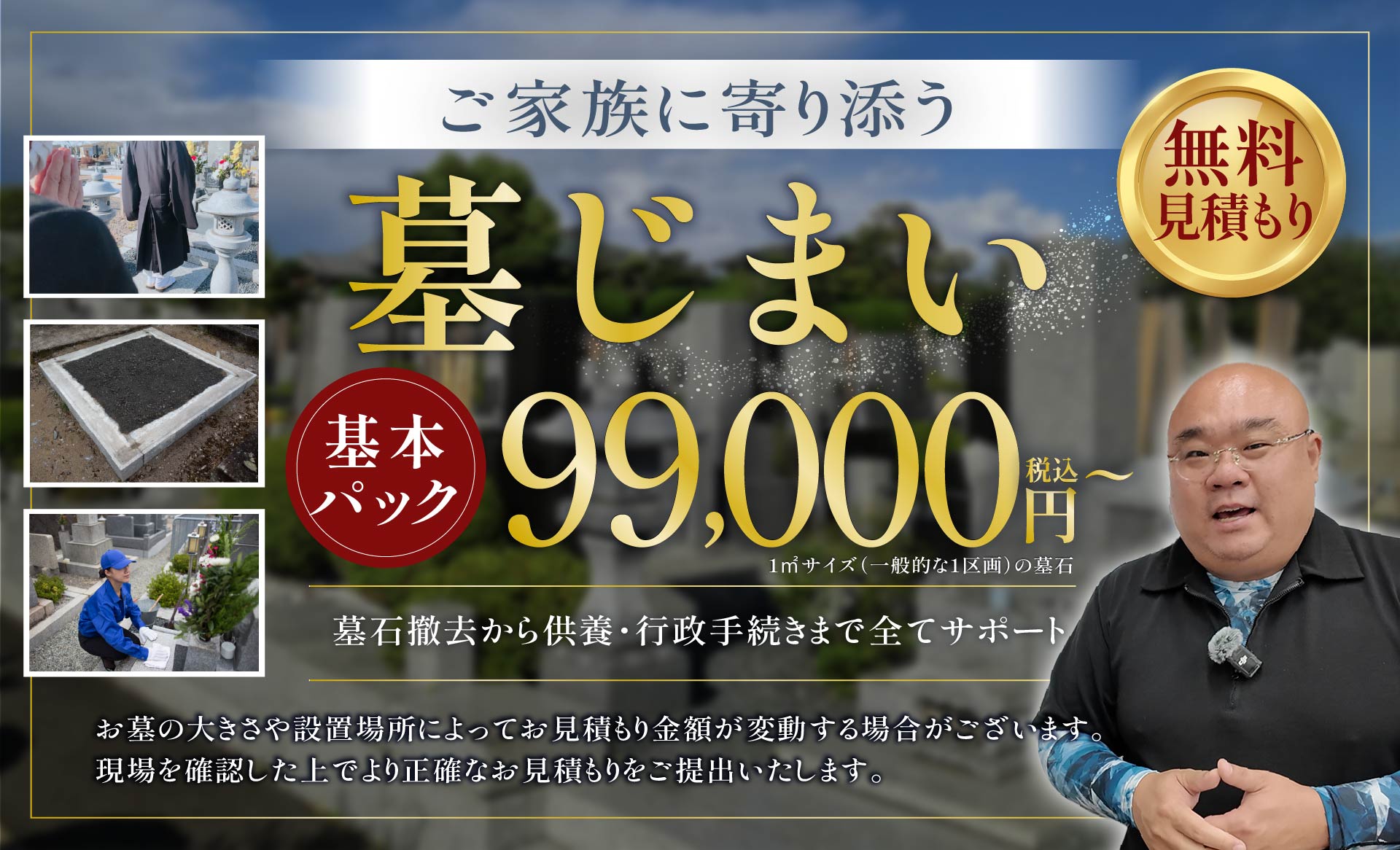| こちらの記事はYouTube動画の文字お越しとなっております。ぜひ本編動画もご覧ください。 |
皆様こんにちは!ウラシコチャンネルです。今日は「家を解体したいけど、何から始めればいいの?」「手続きって面倒なの?」とお悩みの方に向けて解説していきます。
私たちウラシコにも、このようなご相談をよくいただきます。そこで今回は、家を解体するための流れや必要な手続き、そしてスケジュール感について、初めての方でも安心して進められるよう、実際の現場の流れに沿ってわかりやすくご紹介していきます。ぜひ参考にしてみてください。
解体工事の適切な進め方
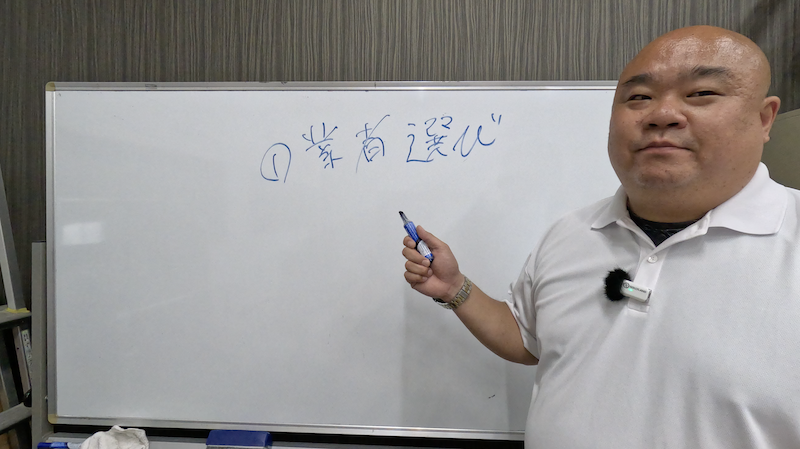
いきなりですが、「解体って頼めば全部やってもらえるんじゃないの?」と思われる方も多いですよね。実際にはそう単純ではありません。補助金制度の利用も含めて、段階的に進めていく必要があります。
家の解体にはいくつかのステップがあります。「解体の相談 → 見積もり依頼 → 契約 → 届け出 → 工事 → 完了後の手続き」という流れです。
工事そのものは、一般的に2週間から1ヶ月程度で完了するケースが多いですが、その前後の準備や手続きを含めると、全体では1ヶ月から2ヶ月ほどを見ておくと安心です。
解体業作選びと見積り
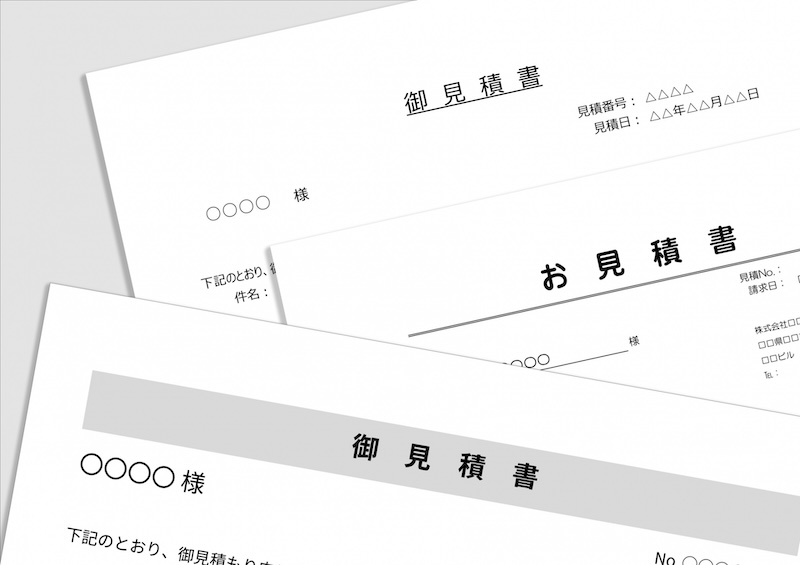
まず最初は 業者選びと見積もり依頼 からです。「なぜ解体したいのか」「老朽化の度合い」「敷地の状況」などを伝えて、業者に現地確認をしてもらいます。見積もりは基本的に無料で対応している業者がほとんどです。
ただし、1社だけに依頼するのではなく、必ず複数の業者に依頼して比較することをおすすめします。その際、金額だけで判断するのではなく、対応の丁寧さや説明のわかりやすさ なども重要な判断材料になります。
特に注意したいのが、極端に安い見積もりを出してくる業者です。契約前に「追加費用は発生しません」と明記してもらったり、しっかり確認をとることが大切です。
例えば、他社が「300万、310万、320万」といった金額を提示しているのに、1社だけ「100万円」と極端に安い見積もりを出してくる場合。こうしたケースでは、後から追加費用を請求される可能性が高いため注意が必要です。
また、ポストに投函されるチラシや、突然の訪問営業で「激安」をうたう業者の中には、後から高額な解体費用を請求するケースも報告されています。こうした業者に引っかからないためにも、事前の情報収集と業者の見極めが重要です。
補助金や助成金のチェック
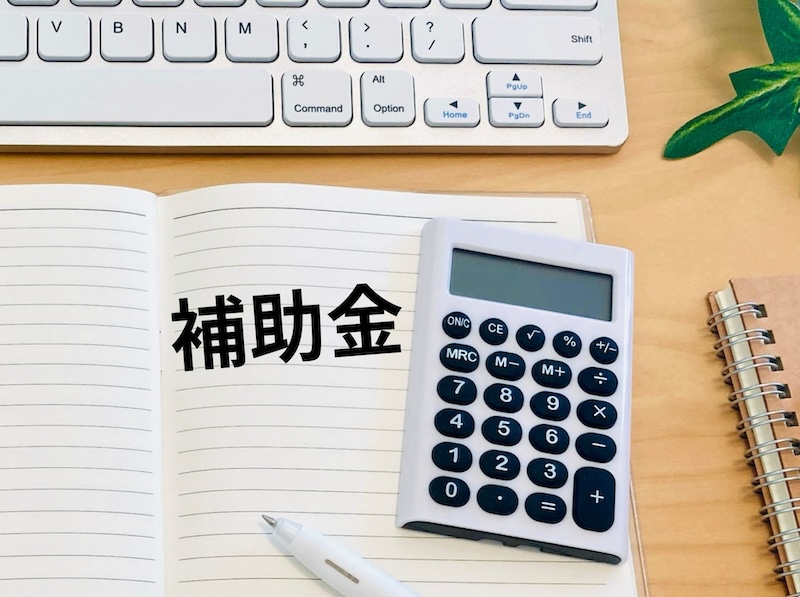
さらに、見積もり依頼と同時に進めたいのが補助金や助成金のチェックです。地域によっては、解体工事に対して費用の一部を助成してもらえる制度がありますので、必ず調べておくと安心です。
ただし、補助金制度を利用するには 事前申請が必要 です。工事が始まってからでは使えないことがほとんどですので、契約前か遅くとも着工前に申請しておく必要があります。
申請の際には、見積書や所有者確認の書類、現況写真などが必要になることが多いです。このあたりは業者がサポートしてくれる場合もありますので、補助制度に詳しい業者かどうか も選ぶポイントになります。
申請が完了すると、市区町村(例:名古屋市など)による審査が行われます。書類に不備がなければ、おおむね2週間程度で結果が出ることが多く、無事に審査を通過すると「交付決定通知書」が送られてきます。
この通知が届く前に工事を始めてしまうと、補助金の対象外となり支給されません。必ず通知が届くまで着工を待つようにしましょう。
解体工事の契約
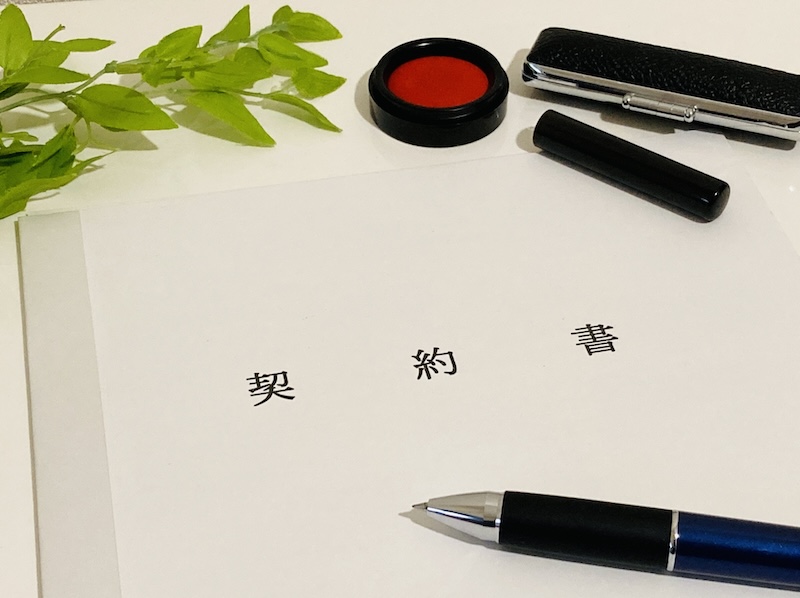
見積もりを済ませ、補助金の確認もできたら、いよいよ工事の契約です。信頼できる業者が決まったら、正式に工事契約を結びます。契約書には 費用・工期・工事範囲 などが明記されていますので、しっかり確認してサインをしましょう。
契約後には、解体工事に必要な届け出や準備を進めていきます。具体的には、建設リサイクル法に基づく届け出、道路使用許可、そのほか関連する各種書類の手続き、そして近隣へのご挨拶などがあります。
さらに重要なのが ライフラインの停止手続き です。電気・ガス・水道を事前に止めておく必要があります。特にガスは危険を伴うため、必ず撤去や閉栓作業を行います。
水道については少し特殊で、解体中に水を撒いてホコリを抑えるために使用することがあります。そのため、完全に止めるのではなく「工事後に撤去」という形を取る場合もあります。ここは事前に業者と相談して決めると安心です。
これらの手続きは、多くの場合、解体業者が代行してくれますので、任せてしまって大丈夫です。ただし、名義や本人確認書類などは施主側での準備が必要です。これらを早めに用意しておくとスムーズに進みます。
工事着工

そして、いよいよ解体工事が始まります。工事の流れは大きく分けて、準備作業→建物本体の解体→整地・清掃という順番で進んでいきます。
まず初日に行うのが、足場の設置や養生シートの取り付けです。これは粉じんや騒音が近隣に広がるのを防ぐための、とても重要な作業です。次に建物内の残置物、つまりゴミや家具などを撤去します。それが終わってから、いよいよ重機を使った建物本体の解体に入っていきます。
「解体工事=ただ壊すだけ」というイメージを持たれがちですが、現代の解体工事は大きく異なります。専門的で繊細な作業が求められ、特に住宅が密集する地域では、粉じんや騒音の抑制、安全管理に細心の注意を払いながら慎重に進める必要があります。近
隣住宅がすぐ隣にあるような場所では、手こわしと重機を併用する作業になるケースも多いです。建物の解体が終わったら、コンクリート基礎の撤去、そして地中に埋まっている配管や埋設物の処理を行います。
もともと木造住宅が建っていた場所では、昔の慣習でゴミを地中に埋めていた、なんてこともよくあります。そのため、工事の最後には 地中埋設物の確認と撤去作業 を行います。ここまでが解体工事の「完了」とされる部分です。
工事完了手続き

工事が終わったら、最後に 法的な手続き が必要になります。代表的なのが「滅失登記」と呼ばれる届け出です。これは「建物が解体され、存在しなくなった」ということを法務局に正式に申請する手続きで、解体後1ヶ月以内に申請することが義務付けられています。
この手続きを放置すると、登記上はまだ建物がある扱いのままとなり、固定資産税がかかり続けたり、売却や建て替えに支障が出る恐れがあります。滅失登記の際には、解体業者が発行する「取り壊し証明書」や、工事前後の写真などが必要です。
信頼できる業者であれば、これらの書類もきちんと用意してくれますので、安心して任せることができます。また、業者の中には司法書士と連携して、滅失登記の手続きまでサポートしてくれるところもあります。
さらに補助金を申請した場合は、完了報告と精算の手続き が必要です。解体完了後の写真や領収書、工事報告書などを自治体に提出して、初めて補助金が正式に支給される流れになります。ここまでやって、ようやく「解体工事がすべて完了した」と言えるわけです。
最後に
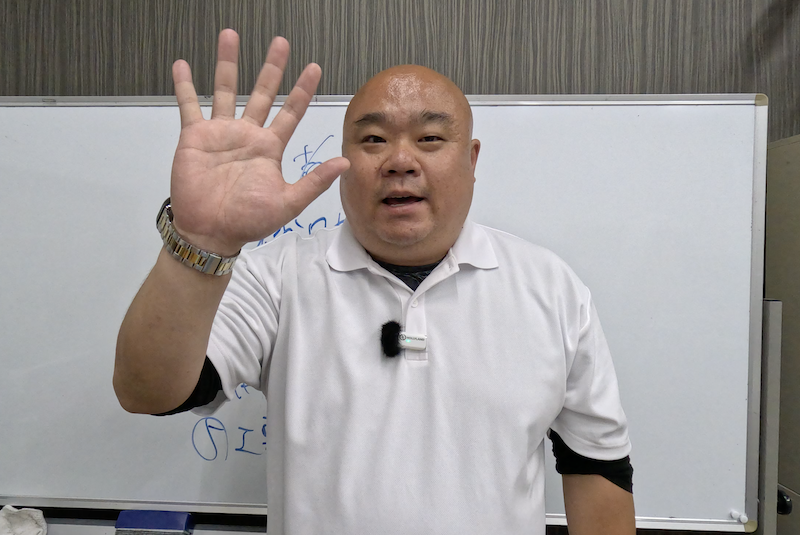
今回は家を解体する際の流れを 5つのステップ に分けてご紹介しました。最後にもう一度ポイントをまとめます。
業者選びと見積もり
複数の業者から見積もりを取り、金額だけでなく対応の丁寧さも比較しましょう。
補助金制度の確認と申請
補助金が使えるかを確認し、申請は必ず着工前に行ってください。
契約と各種届け出
契約後は、建設リサイクル法などの届け出、そして電気・ガス・水道といったライフラインの停止手続きを進めます。
解体工事の実施
足場や養生の設置、残置物の撤去を経て、建物の解体を安全に行います。
工事完了後の手続き
滅失登記の申請や、補助金利用時の完了報告を忘れずに行いましょう。
この流れをしっかり守れば、解体工事はスムーズに進められます。特に補助金を使う場合は「着工前の申請」が必須ですので、ここは絶対に注意してください。
まとめ
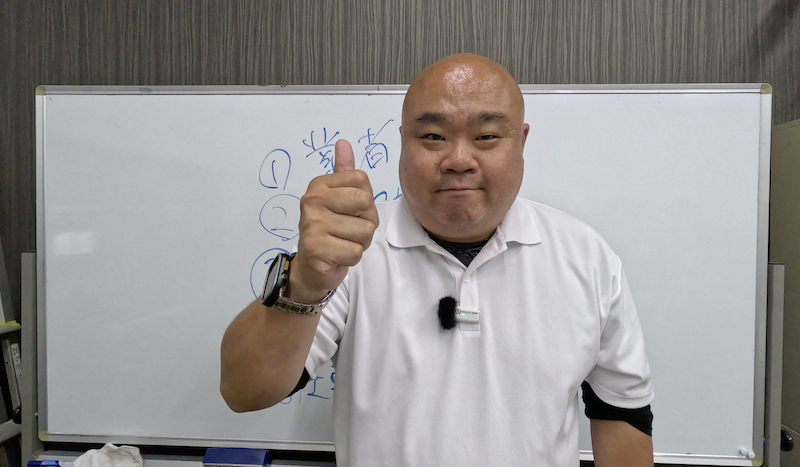
ここまでしっかり対応していただければ、解体工事はスムーズに進められると思います。ぜひ参考にしてみてください。もちろん、お住まいの解体工事は私たちウラシコにお任せいただければ幸いです。