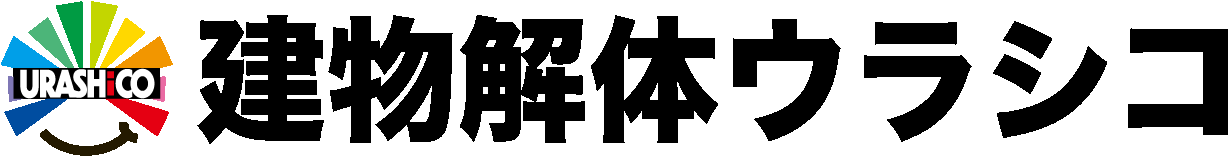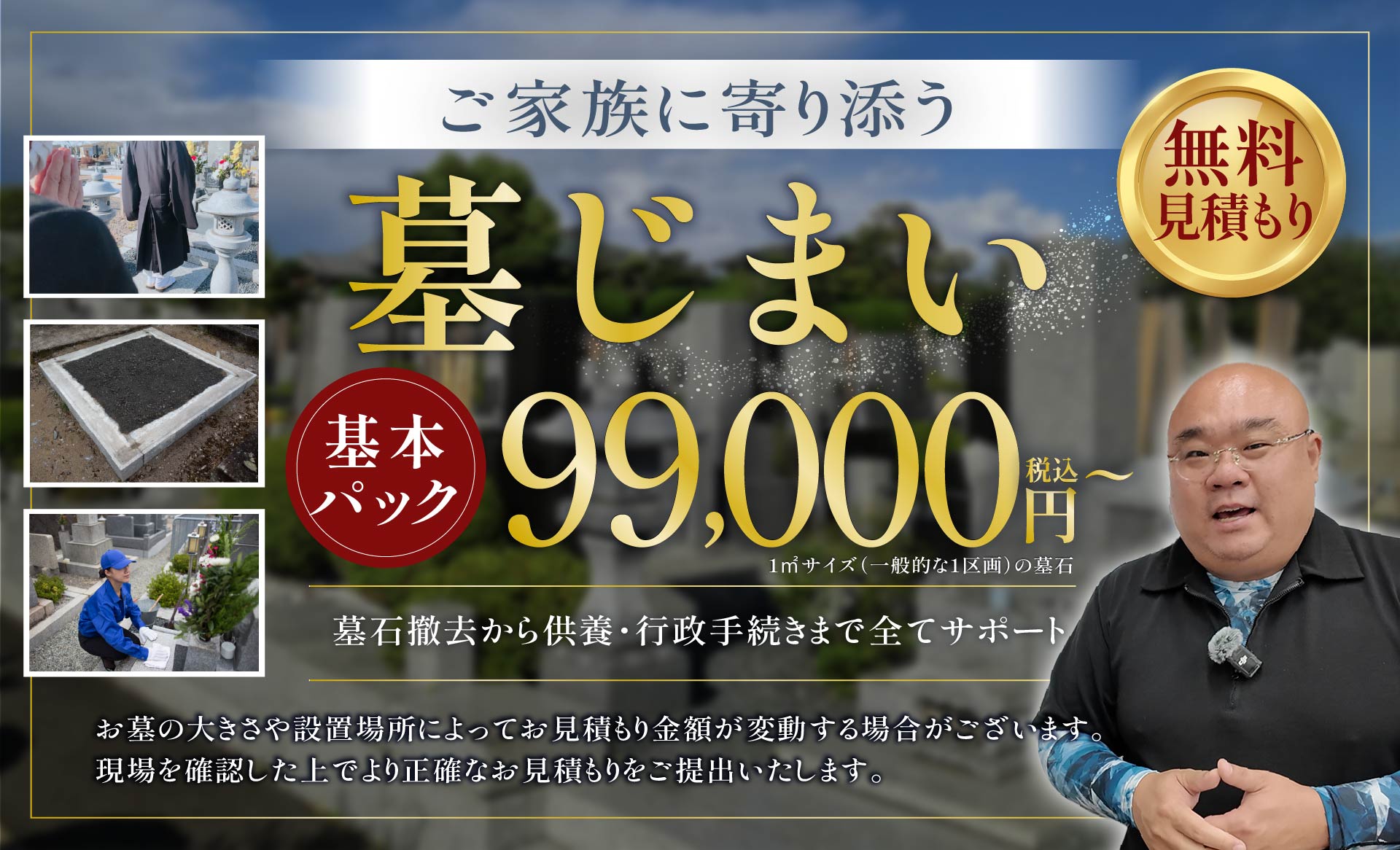| こちらの記事はYouTube動画の文字起こしとなっております。ぜひ本編動画もご覧ください。 |
皆様、こんにちは。株式会社ウラシコです。今回は初心者向けに、アスベストの見た目や特徴、そして安全に対処する方法について解説していきます。
ただし、アスベストは見た目で識別できる場合もありますが、素人の誤った判断や判別作業は非常に危険です。今回の内容はあくまでも参考程度とご理解いただき、最終的な判断は必ず調査資格を持ったプロにご相談されることをおすすめします。
アスベストは見た目で判断できる?
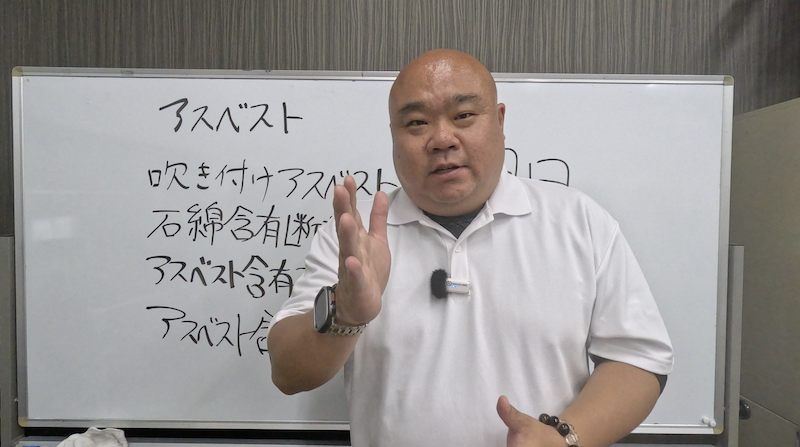
早速ですが結論から言うと、見た目で分かる場合もありますが、分かりにくい箇所や似たような建材も多いため注意が必要です。
アスベストは見た目だけで判断するのが非常に難しい素材です。見た目が似ている安全な建材も多いため、誤って壊してしまうと健康リスクが一気に高まってしまいます。特に古い建物では慎重な確認が欠かせません。
近年は建物の老朽化が進み、立て直しやリフォームの機会が増えてきました。その中でアスベストに触れるリスクも高まっており、正しい知識と対応がますます重要になっています。
アスベスト調査の義務化について

この問題を重く受け止め、令和4年からは解体作業に伴う調査と、その結果報告が義務付けられています。古い建物の場合は必ず調査を受けるべきです。
木造の建物であれば外壁の塗装や床材、RC造(鉄筋コンクリート造)の場合はロックウールの吹き付け断熱材など、アスベストが使われている可能性が非常に高いからです。「古い建物だな」と思ったら、まずは「アスベストがあるかもしれない」と考えていただくことが重要です。
アスベストの見た目について
それでは、「アスベストってどんな見た目をしているのか?」という点について説明します。よく「綿のような形状」をイメージされる方もいますが、実際には非常に粒子が細かく、さまざまな形に加工されています。代表的なものをいくつかご紹介します。
吹き付けアスベスト

それではここから、それぞれの特徴について詳しく解説していきます。まずは 吹き付けアスベスト からです。アスベストにセメントを混合して吹き付けることで、断熱や吸音の目的で使われていました。
見た目は塊のような綿のようで、柔らかく、劣化すると埃のように垂れ下がってきます。そのため非常に飛散しやすいのが特徴です。さらにアスベスト濃度も高く、除去には「レベル1」と呼ばれる最も厳しい対策が必要になります。
石綿含有断熱材

アスベストを繊維状に加工した断熱材や保温材で、見た目は繊維がまとまったシート状をしています。主にダクトの配管や、配管の曲がり部分、L型配管の継ぎ手などに使用されていました。通常はカバーや養生で覆われているため、外からは劣化や繊維の露出が確認できず、判断が難しい場合も多いです。
石綿含有断熱材は、吹き付けアスベストに比べると飛散リスクは低いですが、中にはアスベスト含有率が90%を超える製品もあります。そのため、作業時には徹底した暴露対策が必要です。
石綿含有スレート板

これはアスベストをセメントなどと混ぜてボードやプレート状に成形した建材です。見た目は固形でプレート状をしており、破損や劣化がない限り、アスベストが飛散するリスクは比較的低いとされています。
ただし、セメントに混ぜ込まれているため、見た目でアスベストの有無を判断するのは非常に難しいのが特徴です。現在流通している製品には裏面に「アスベストなし」と表示されているものもありますが、古い製品にはその表示がないため、検体検査をしなければ確実な判断はできません。
特に波型スレートは屋根や外壁に多く使われており、劣化や損傷がなければ飛散の心配はありません。しかし、劣化が進んでボロボロに崩れている場合には、「囲い込み」や「封じ込め」といった対策が必要になります。
アスベスト含有床材

これは「ビニールアスベストタイル(VAT)」と呼ばれ、ビニール樹脂にアスベスト繊維を混ぜて作られた床材です。1950年代から1980年代にかけて、工業施設や商業施設、住宅など幅広く使われてきました。比較的近年まで使用されており、2006年になってようやく製造と使用が原則禁止となっています。
見た目の特徴としては、表面が滑らかで色や模様がついていることが多く、一見すると普通のビニールタイルと区別がつきにくいです。ただし、裏面がザラザラしている ことが特徴で、そこにアスベストが含まれている可能性があります。とはいえ、正確に判断するには成分調査が必要です。
イメージとしては、デパートの床などに使われている小さめのタイル。そうした場所でよく使用されていたものです。家庭の一般的な居住空間ではアスベスト床材はあまり使われていませんが、水回りや土足で歩く場所などには使用されていたケースがあります。もしそういった床材が残っていたら注意して確認する必要があります。
アスベストの見た目以外の判断基準
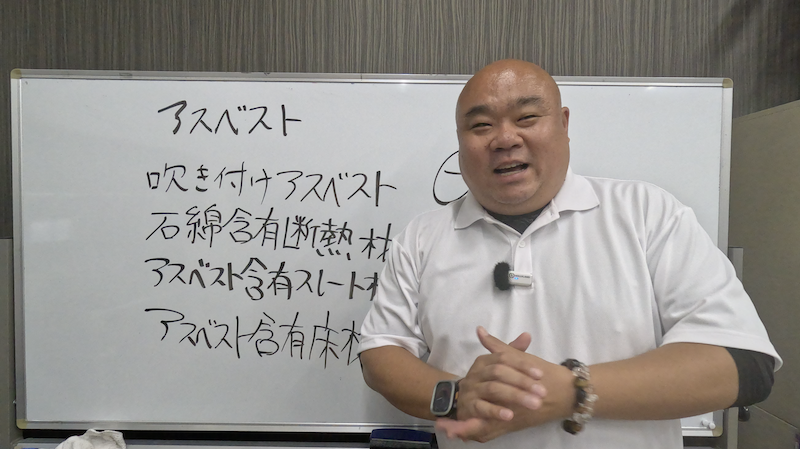
ここまでで見た目の特徴について説明しましたが、やはり「見た目だけでは判断が難しい」と感じられたと思います。では、小さなヒントにはなるものの、見た目以外での判断基準 はあるのでしょうか?主な判断基準は3つあります。
設計図書や仕様書の確認
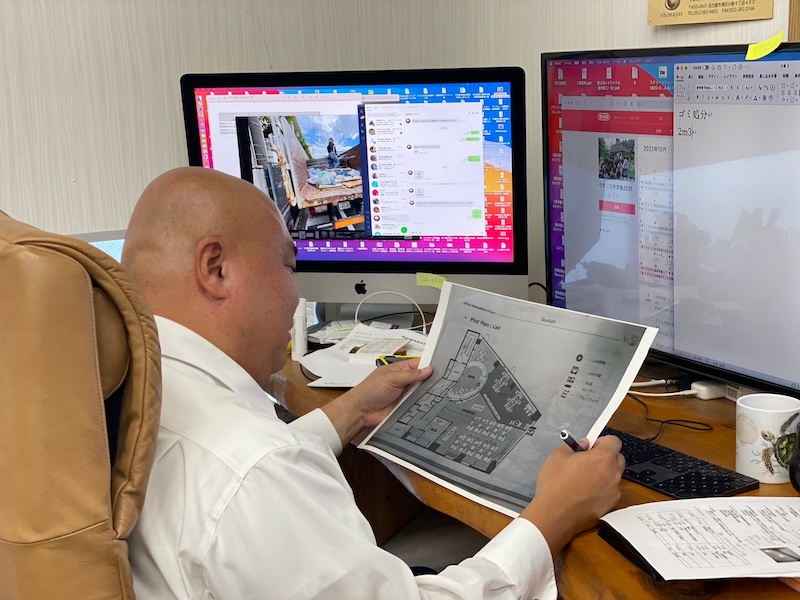
建物の設計図や仕様書が残っている場合は確認してみましょう。建設着工日が2006年(アスベスト全面禁止)以前の場合は、どの建材にアスベストが使われている可能性があるのか特定する必要があります。
特に1955年~1975年頃に建てられた建物は、アスベストが使われている可能性が非常に高いです。1975年~1995年頃の建物でも、断熱材や吸音材、天井や壁などに使用されているケースがありました。
2000年以降はアスベストの危険性が広く指摘され、使用される可能性はかなり低くなりました。ただし、2006年の全面禁止まではゼロではありません。2000年~2006年に建てられた建物でも含有の可能性があるため注意が必要です。
2006年に全面禁止となりましたが、それ以前の建物ではアスベストが使われている可能性が十分にあります。調査を進める際には、まず 設計図や仕様書から使用されている建材を洗い出す ことが重要です。
その後、特定した建材を国交省の「石綿含有建材データベース」で検索し、アスベストの有無を確認することができます。仕様書があれば、どの建材に含まれているかが比較的分かりやすいですね。
アスベストマークの確認

では、仕様書がない場合はどうすればいいのでしょうか?その場合は、目視で 「アスベストマーク」 があるかどうかを確認してみましょう。一部のアスベスト含有製品には、このマークが印字されています。
例えば「A」という大文字や小文字のマークで示されることがあります。もし「Aマーク」があれば、アスベストを含んでいる建材の可能性が高いと考えられます。ただし注意点として、すべての製品にマークがあるわけではありません。マークがないからといってアスベストを含んでいないとは限らないため、過信は禁物です。
製造番号を確認し製造元に問い合わせ

そんな場合に最後の手段としてご紹介できるのが、製品名や製造番号を確認し、製造元に問い合わせる方法 です。天井材や床材には基本的に製品名や製造番号が記されています。これを確認できれば、製造元に問い合わせることでアスベストの含有有無を確認することが可能です。
一方で、インターネット上には「実際に触ってみる」「擦ってみる」「針を刺して確認する」といった方法が紹介されていることもあります。しかしこれは非常に危険です。アスベストを吸引してしまうリスクがあるだけでなく、確証のない不正確な判断にしかなりません。絶対に自己流でこうした作業を行わないようにしましょう。
少しでも「怪しい」と感じたら、自己判断は避けて、必ず資格を持った専門業者に相談し、調査を依頼することが大切です。国がアスベスト調査資格を厳しく規定しているのも、それだけ危険性が高いからです。
アスベストを見つけたときの正しい対処法

まず大前提として、アスベストを見つけたからといって、必ずしも直ちに除去しなければならないわけではありません。アスベストを見つけた場合は、まず 飛散の危険性があるかどうかを冷静に確認すること が大切です。最終的な判断は、有資格者による書面調査や分析調査を総合的に行う必要があります。
アスベスト調査が義務化されてからは、分析調査を行う会社も多く増えています。インターネットで検索すればすぐに見つけられるでしょう。調査だけであれば数万円以内で、検体採取と研究機関での分析調査を行ってくれます。
もしアスベスト含有の可能性が高いと判断された場合は、「石綿障害予防規則」 に従い、除去・封じ込め・囲い込みといったいずれかの措置を講じることが推奨されています。
まとめ
では最後に、今日の内容をまとめます。アスベストの代表例として、吹き付けアスベスト、石綿含有断熱材、スレート材、アスベスト含有床材 があります。
見分け方・判断基準として、
1. 建物の設計図や仕様書を確認する
2. 「Aマーク」の有無をチェックする
3. 製品名や製造番号を確認し、製造元に問い合わせる
4. 不明な場合や含有の可能性がある場合は、必ず専門家に相談する
最後に
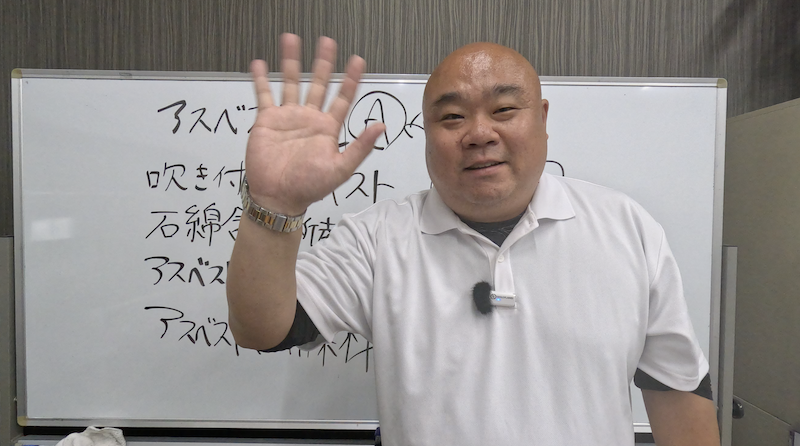
アスベストの調査や各種除去工事のご相談は、ぜひウラシコまでお気軽にご連絡ください。石綿含有建材調査者の資格を持つ専門家が対応いたしますので、安心してご相談いただけます。
解体業者さまや内装業者さまなど、同業者の方からのご連絡も歓迎しております。「アスベストをなくして、明日をベストに!」そんな思いで、これからも取り組んでまいります。